インフォデミック
情報(information)と流行(epidemic)を組み合わせた造語で、特にインターネットやSNS上で、誤った情報やデマ、噂などが急速に拡散される現象を指します。世界保健機関(WHO)は、インフォデミックを「事実と虚偽の情報が入り混じり、急速かつ広範囲に拡散することで、人々の健康や社会に悪影響を与える情報過多の状態」と定義しています。
インフォデミックは、新しい出来事や危機的な状況が発生した際に起こりやすく、人々の不安や恐怖心を煽るような情報が拡散されやすい傾向があります。例えば、新型コロナウイルス感染症のパンデミック時には、ワクチンの安全性や感染経路に関する誤った情報が大量に拡散され、人々の行動に影響を与えました。
インフォデミックは、人々の健康や社会に悪影響を与えるだけでなく、民主主義の基盤を揺るがす可能性もあります。誤った情報やデマが拡散されることで、人々は正しい判断を下せなくなり、社会の分断や対立が深まる可能性があります。
インフォデミックが発生する人間の脳の仕組み
「脳のOSが、時代に追いついていない」
我々の脳の基本的なOSは、数万年前の狩猟採集時代、つまり「小さく、危険な世界」で生き抜くために設計されました。
その世界では、目の前の情報(例:茂みがガサガサ揺れる)に対して、
「ライオンかもしれない!すぐ逃げよう!」
と瞬時に判断し、行動する個体が生き残りました。
「本当にライオンだろうか?データは?証拠は?」
と吟味するコストは、自らの死に直結していたのです。
この「疑うよりも信じる方が生存率が高い」という環境で最適化された脳が、安全で情報過多な現代社会という、全く異なる環境で動いています。これが、インフォデミックの本質的な原因、つまり「進化的ミスマッチ」です。
本質的な3つの「バグ」
この古いOSには、インフォデミックを誘発する、主に3つの根源的な「バグ」が存在します。
① エネルギーを節約する「認知のショートカット」
脳は膨大なエネルギーを消費する器官であり、常に省エネを心がけています。そのため、物事を深く考えず、直感や感情、分かりやすい話に飛びつく「ヒューリスティック」というショートカット機能が標準装備されています。
インフォデミックで拡散される情報は、このショートカット機能にハッキングを仕掛けるように作られています。複雑な現実を単純な善悪二元論に落とし込み、考える手間を省いてくれるため、我々の脳は心地よさを感じ、それを容易に受け入れてしまうのです。
② 「仲間」を識別し、結束するための物語
人間は社会的な動物であり、生存のためには集団に所属することが不可欠でした。その中で「情報」や「物語」は、単なる事実の伝達手段ではなく、「誰が仲間で、誰が敵か」を識別し、集団の結束を高めるための道具でした。
あるデマを信じ、共有することは、「私はあなたと同じ価値観を持つ仲間です」という忠誠の証となります。特に社会が分断している状況では、情報の真偽よりも、その情報が所属集団の結束を強めるかどうかが優先されます。事実を指摘することが、仲間への裏切りと見なされることさえあるのです。
③ ランダムな世界に「意味と秩序」を見出す欲求
世界で起こる出来事の多くは、本来、ランダムで、特定の意図や意味を持たないものです。しかし、人間の脳は無秩序や偶然を極端に嫌い、全ての物事に因果関係や物語(ナラティブ)を見出そうとします。
陰謀論のような壮大なデマは、この欲求を満たしてくれます。複雑で無秩序な現実よりも、「世界の裏で全てを操る悪の組織がいる」という歪んだ秩序の方が、脳にとっては理解しやすく、ある種の安心感さえ与えるのです。
インフォデミックとは、知性の欠如や情報リテラシーの低さだけの問題ではなく、生存のために最適化された我々の脳の基本設計そのものが、現代の情報社会との間に起こす、避けがたいシステムエラーです。
【関連記事】
未完のテクノロジーが導く未来:インターネットがもたらす社会の分断と民主主義の危機
映像編集は確証・認知・正常化バイアスを利用する事実の再編
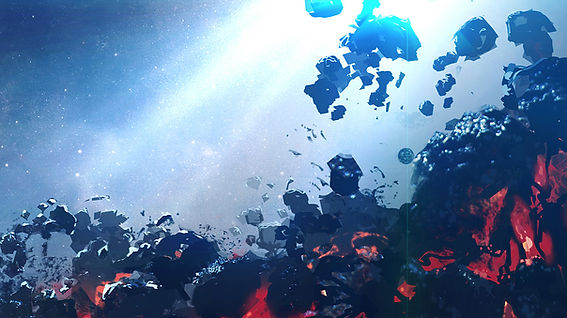
【関連情報】
映像制作者として注意すべきこと
1. 「信頼」と「誠実さ」を最上位の価値とする
インフォデミックは、信頼の喪失から生まれます。視聴者は、映像の作り手が誠実であるか、都合の良い情報だけを切り取っていないかを鋭く見抜きます。特に企業活動に関わる映像は、その企業の信頼そのものを左右します。
「都合の悪い真実」から逃げない: 完璧な企業や製品はありません。メリットだけでなく、課題や制約についても誠実に言及することで、かえって信頼は深まります。
出所を明示する: データや引用を用いる際は、必ずその出所(機関名、調査年など)を明確に示しましょう。これにより、視聴者が情報を検証する手助けとなり、映像の信憑性を高めます。
誇大表現を避ける: 「世界初」「業界最高」といった断定的な表現は、正確な根拠がなければインフォデミックの温床となり得ます。事実に基づいた、慎重な言葉選びを心がけるべきです。
2. 「複雑な現実」を「単純化」しすぎない
脳の省エネ機能(認知のショートカット)に迎合しすぎると、表面的な情報や感情に訴えるだけのコンテンツになってしまいます。私たちは、複雑な現実を解きほぐし、視聴者が自ら考えるきっかけを提供しなければなりません。
多角的な視点を取り入れる: 一つの視点だけでなく、多様な関係者(顧客、従業員、専門家、第三者機関など)の声を織り交ぜることで、より深く、多層的な物語を構築できます。
「Why」を語る: 「What(何を)」や「How(どうやって)」だけでなく、「Why(なぜ)」を深く掘り下げましょう。製品やサービスの背景にある哲学や社会的な意義を伝えることで、視聴者は単なる情報消費から、より深い理解へと進みます。
「二元論」の罠を避ける: 「善 vs 悪」「自社 vs 他社」といった単純な対立構造は、感情的な共感を得やすい一方で、インフォデミックの温床となります。視聴者を分断するのではなく、共感や共創の土壌を作る映像を目指すべきです。
3. 「物語の力」を正しく活用する
人々が物語に意味を見出す欲求は、インフォデミックの原動力となる一方で、正しい情報を伝える上でも強力な武器となります。私たちは、この力をポジティブな方向で活用する責任があります。
「仲間意識」を健全に醸成する: 映像を通じて、単なる製品のファンではなく、ビジョンや価値観を共有する「仲間」を形成しましょう。これは、企業と顧客の長期的な関係性を築く上で不可欠です。
「共感」の物語を紡ぐ: 企業の理念や技術の裏側にある、人々を動かす情熱、試行錯誤のプロセス、そして失敗から学んだ物語を正直に描くことで、視聴者は感情的に繋がりを感じます。
「信頼できる語り手」になる: 映像制作者自身が、視聴者にとって「信頼できる語り手」としての役割を担いましょう。一方的な情報伝達ではなく、対話を生むような構成を意識することで、インフォデミックへの抵抗力を高めることができます。
4. 映像が加担する事例
ディープフェイク動画:AIで生成された偽の映像が、著名人や政治家の発言を捏造し、SNSで急速に拡散される。
切り取り・文脈の削除:発言や出来事の一部だけを切り取った映像が、本来の意図と異なる印象を与えて拡散される。
古い映像の流用:過去の災害や事件の映像を、最近の出来事として誤って拡散し、パニックを引き起こす。
演出映像の事実化:ドラマやCG、演出された映像が、実際の出来事として誤認され拡散される。
誤解を招く編集:因果関係のない映像を並べたり、ナレーションで誤った解釈を加えたりして、陰謀論や誤情報を強化する。

